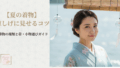せっかくキレイに着付けた浴衣も、動くたびに崩れてしまっては台無しですよね。
この記事では、
初心者さんでも実践しやすい「着崩れを防ぐコツ」と「着崩れたときの直し方」を紹介します。
外出前のチェックや、出先でのお直しにも役立つ内容なので、ぜひ予習・復習にご活用ください。
「着物」と「浴衣」の違いを知っておくと、浴衣ならではのポイントが理解しやすくなります。
▶【解説】着物と浴衣の違いとは?素材・着用シーン・着方を解説
浴衣が着崩れる原因とは?
浴衣は、1枚の布を体に沿わせて着るシンプルな構造のため、
いつものように大股で歩いたり、勢いよく腰を下ろしたりすると、どうしてもズレやすくなります。
特に着崩れやすいのは、歩き方や座り方などの動作に無意識のクセが出たときなんです。
また、腰ひもが緩い・補整が足りないと、時間が経つにつれて胸元や裾が乱れがちです。
着崩れを防ぐ基本は「正しい姿勢」にあります。
猫背になると老けて見えるだけでなく、衣紋が詰まって衿元が崩れる原因にも。
軽く胸を張り、肩甲骨を寄せて背筋を伸ばし、
頭を上から引っ張られているような意識で首を立てましょう。
姿勢と所作を意識するだけで、着崩れが減るだけでなく、所作も美しく見えますよ。
着崩れを招きやすいポイント
浴衣は一枚布を体に巻きつける構造のため、洋服感覚の動きではズレやすい
大股で歩いたり、勢いよく腰を下ろすなどの動作で着崩れしやすい
着付け時の腰ひもの締め不足や補整不足も原因になる
姿勢が崩れると、衿元や衣紋が乱れやすくなる
基本の手順をおさらいしておくと、崩れにくくなります。
▶【写真でわかる】初心者でも失敗しない浴衣の着方ガイド
大股で歩くと裾がズレやすい
浴衣を着て歩くときは、歩幅を狭く、内股気味に歩くのが基本です。
普段どおりに大股で歩いたり、外股で足を踏み出してしまうと、
裾が広がって着崩れの原因になります。
とくに急いでいるときは、大きな動きになりがちなので要注意です。
草履を引きずるようなすり足にする必要はありませんが、
裾が割れない程度の小股でまっすぐに歩くことを意識してみてください。
また、着付け後に軽く足を肩幅に開いて2〜3回屈伸をする「裾割り」をしておくと、
動きやすさがぐんとアップします。
裾割り(すそわり)とは?
浴衣を着付けたあと、足を肩幅程度に開いて2〜3回軽く屈伸をする動作のことです。生地に余裕ができて、歩いたり動いたりするときの動きやすさが格段にアップします。
💡コツ:背中に1本の棒が通っているようなイメージで姿勢を正し、膝を少し緩めると歩き出しが自然になります。裾が乱れにくく、美しい所作にもつながりますよ。
低い椅子にドサッと座ると腰紐が緩みやすい
浴衣を着ているときに注意したいのが、椅子への座り方です。
特に、低い椅子に勢いよくドサッと座ると、腰まわりの衝撃で腰紐が緩みやすく、
裾やおはしょりが崩れてしまう原因になります。
座るときのポイントは「浅めに座る」こと。
深く座ると腰まわりの布が引っ張られて着崩れやすくなるうえ、背もたれに帯が押し潰されてしまうおそれもあるため、
浅く腰かけて背もたれにもたれない姿勢を心がけましょう。
車やタクシーの乗り方も意識して
乗り込むときは、まずシートに背を向けた状態でお尻から腰を下ろします。
その後、体を15度ほど回転させて足を車内に入れれば、足を大きく開くことなく裾を乱さず乗り込むことができます。
この所作を意識するだけで、着崩れを防げるだけでなく、美しい所作としても好印象ですよ。
💡コツ:背中に1本の棒が通っているようなイメージで姿勢を正し、膝を少し緩めると歩き出しが自然になります。裾が乱れにくく、美しい所作にもつながりますよ。
腕を上げると衿元がズレやすい
衿元の着崩れは、実は「手を高く上げるときの動き方」が原因のひとつかもしれません。
私たちはつい、手を上げるときに肩ごとグッと力んでしまいがちですが、浴衣や着物を着たときはこの動きが衿元を引っ張ってしまい、衣紋が詰まったり、胸元が緩んだりしやすくなります。
そこで意識したいのが、「肩」ではなく肩甲骨から動かすということ。
肩甲骨を使って腕を動かすようにすると、手が上がっても肩はスッと下がり、
首まわりが引っ張られにくくなるため、衿元の着崩れを防げます。
この「手が上がるほど、肩は下がる」という一見逆のようなバランスが、
実は所作の美しさにつながります。
💡コツ:
- 衿元が引っ張られそうなときは、反対の手で軽く衿を押さえるだけで着崩れ防止に◎
- 髪を結ぶときや物を取るときは、肩甲骨から動かす意識を持って。自然と動きが美しくなります。
しゃがむときに着崩れやすい
物を拾ったり、床に近い場所に手を伸ばすとき、
無意識にしゃがむ動作は着崩れの原因になりがちです。
特に勢いよくしゃがみ込むと、裾が広がったり袂が床についたりしてしまいます。
しゃがむ際には、上前(うわまえ)をそっと持ち上げてから動くのがポイント。
右足を半歩後ろに引き、片膝を軽く折るように静かにしゃがむと裾が広がりにくく、上品に見えます。
このとき、右手の袂(たもと)が床につかないように意識して手前に引き寄せると、
さらに美しい所作になります。
また、和室での所作には少し違いがあります。洋室では膝をつかずにしゃがむのが基本ですが、
畳の上では両膝をつけて座ることで、より丁寧で清潔感のある印象を与えます。
💡コツ:しゃがむときは「静かに・ゆっくり・優しく」を意識すると、着崩れにくく美しい動作になりますよ。
着崩れを整えるコツ|直すべき“3つの場所”とは?
浴衣は1枚の布を体に巻きつけて着るため、どうしても動くうちに少しずつズレてしまいます。
大切なのは「浴衣は崩れるもの」と割り切って、
外出先でも落ち着いて整えられるようにしておくこと。
着崩れは、生地が引っ張られて緩むことで起こりますが、
正しい順序で元の位置に戻せば意外と簡単に直せます。
まずは胸元(衿・脇)を整え、それから「おはしょり・裾・衿元」の3か所をチェックすれば、
全体の印象がすっきりしますよ。
▶衿元のチェック
腕を大きく動かすことで、両脇下の生地が引っ張られ、帯の上あたりにたるみが生じやすくなります。
このたるみは、衿のゆるみや開きの原因にもなるため、最初にしっかり整えておきましょう。
手順としては、①右手で前身頃の衿を軽くつまんだ状態で、左脇の「身八ツ口(みやつぐち)」と呼ばれる開き部分から左手を差し入れ、②内側からたるんだ生地を持ちます。そのまま、③左右それぞれの脇から外側へたるみを逃がすように引き、脇にたるみを集めていきます。
このたるみ処理をすることで、胸元のシワや衿のズレが改善され、次のお直しステップに進みやすくなります。



▶おはしょりの処理
胸元の生地はおはしょりとつながっているため、
おはしょりを下に引くことで胸元のたるみを整えることができます。
①②③で両脇に逃がしたたるみは、④帯のすぐ下にある脇線辺りのおはしょり部分をつまんで下へ引くことで、さらに整えることができます。左右交互に、片側ずつ均等に引いていくと、浴衣が上半身にきれいに沿いやすくなります。たるみが帯の下へと全体的に流せたら、⑤次はおはしょりの前側を整えましょう。帯の下辺を軽くつまみ、指を差し入れて左右へたるみを流すようになじませます。そのまま指の背で表面をなでるようにすると、おはしょりがすっきりと整います。


最後に、前側の調整が終わったら、衿元の余りを後ろに逃がして仕上げましょう(⑥へ)
▶衿元のゆるみをチェック
最後に、衿元のゆるみをしっかり整えてお直し完了です。
ステップ①~⑤で前面のたるみを整えたら、⑥仕上げに背中側のおはしょり部分を下に軽く引き、衿元の余分な生地を後ろに逃がしましょう。衿元は全体の印象を左右する大切なポイントなので、丁寧に整えてくださいね。
💡ポイント
意外と見落としがちなのが「後ろ姿」。
特にお手洗いの後などは、帯のタレが持ち上がってしまっている場合があります。せっかく前からの着姿が美しくても、後ろ姿で台無しになってはもったいないもの。
外出先でも姿見で全身をチェックし、帯のタレが正しい位置にあるかを確認しましょう。

まとめ:着崩れの原因を知れば、直し方も怖くない
浴衣の着崩れは、「動く」「引っ張られる」「ゆるむ」ことで誰にでも起こる自然なことです。
でも、崩れる原因と整える順番を知っていれば、落ち着いて簡単にリセットできます。
まずは脇(衿元)→おはしょり→衿の後ろの順に整え、たるみを外側へ逃がしていくのがポイント。
後ろ姿のチェックも忘れずに行えば、浴衣姿に自信が持てます。
大切なのは、“完璧”を目指すよりも、“自分で整えられる安心感”が大事です。
浴衣でのおでかけは、ほんの少しの動き方やしぐさの工夫で快適になります。
いざという時の直し方も知っておけば安心してお出かけできますよね。
気負わず、崩れたら直すくらいの気持ちで、浴衣のひとときを過ごしましょう。