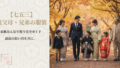[PR]
夏の着物のお手入れ、「汗が染み込んでいるか不安」「このままタンスに入れていいの?」と悩んでいませんか?
お気に入りの一枚を長く楽しむためには、正しいケアと保管が欠かせません。
大切な着物を美しく保つには、日々の正しいお手入れと保管が鍵となります。
夏の着物は、汗や湿気の影響を受けやすい繊細な素材です。
でも、ちょっとしたポイントを知っておくだけで、美しい状態をキープできます。
この記事では、着用後すぐにできる簡単なお手入れから、プロに頼むべき汚れの見極め方、そして長期保管のコツまでを、着付け師の経験をもとにやさしく解説します。
読んだその日から実践できる内容ばかりです。
ぜひ最後までチェックして、今年の夏はお気に入りの着物で快適にお出かけを楽しんでくださいね。
着用直後が命!汗と湿気を残さない「即日ケア」

夏の着物には、単衣(ひとえ)と薄物(うすもの)の2種類があります。
単衣は裏地のない一枚仕立てで、軽く涼しく着られるのが特徴です。
主に6月と9月に着用され、初夏や残暑の季節にぴったりの着物です。
一方、薄物は特に暑さの厳しい7月と8月に登場します。
代表的な素材は絽(ろ)や紗(しゃ)、麻などで、通気性がよく透け感のある涼やかな印象ですよね。
正絹・綿・ポリエステルなどさまざまな素材があり、最近は家庭で洗えるタイプも増えています。
ただし、薄物は織り目が粗く繊細なので、お手入れの際は引っかけや摩擦に注意が必要です。
こうした夏の着物は、軽くて涼しい反面、汗や湿気の影響を受けやすい素材です。
見た目がきれいでも、汗が残ると黄ばみやカビの原因になることがあります。
特に薄物は、汗や湿気を吸い込んだまま放置すると、繊維が傷みやすくなるため、注意が必要です。
単衣・薄物に多い素材別の注意点(麻・絹・ポリエステル)

夏の着物に使われる素材には、麻・絹・ポリエステルなどがあります。
麻は水に強く、自宅で洗えるのが魅力ですが、シワになりやすいのが難点。干すタイミングとアイロンの温度管理がポイントです。
絹(絽・紗)は上品な光沢が魅力ですが、汗や湿気で黄変しやすいため、着用後は即日ケアが欠かせません。
ポリエステルは近年人気の素材で、自宅で洗える手軽さが魅力。ただし、熱に弱く静電気が起きやすいため、アイロンや保管時には注意が必要です。
それぞれ質感や通気性が異なり、お手入れ方法も少しずつ違います。
素材の特性を知っておくことで、汗や湿気によるトラブルを防ぎ、長く美しい状態を保てます。
ここでは、単衣や薄物によく使われる3つの素材別に、扱うときの注意点を紹介します。
麻の着物のお手入れと扱い方
軽くて涼しく、見た目もおしゃれなのが麻の着物。さらに自宅でお手入れできるのが大きな魅力です。
汗をかく季節でも、自分でケアできれば安心ですね。
ここでは、麻の着物を長く美しく保つための簡単なお手入れ方法を紹介します。
1.汗取り(毎回のケア)
汗をかいた部分だけをケアする方法です。
襟や脇など汗が気になる部分を、霧吹きで軽く湿らせ、乾いた布でトントンと押さえるだけ。
汗をバスタオルに移すようにして、水分と汚れを取ります。
毎回洗わなくても、汗取りだけで十分きれいに保てます。
2.洗い方(シーズン終わりに)
基本は水洗いがおすすめ。お湯を使うと色あせや毛羽立ちの原因になります。
手洗いの場合は、たたんだまま水に溶かした中性洗剤でやさしく押し洗いします。
摩擦を避け、すすいだ後はバスタオルで水分を吸い取るようにしましょう。
洗濯機を使う場合は、**洗濯ネットに入れて「弱水流」や「ドライコース」**で短時間脱水(1分以内)。
強く脱水するとシワが残るので注意が必要です。
3.干し方
干すときは着物ハンガーや物干し竿にかけ、
袖山・肩山の布目を通してトントンと形を整えながら干すのがコツ。
麻特有の自然なシワは、風合いとして楽しむのがおすすめです。
気になる場合は霧吹きで軽く湿らせると自然に整います。
㊟麻の着物は「ノーアイロンが基本」という意見と、「高温アイロンOK」という意見があり、迷う方も多いでしょう。
着物の生地にもよりますが「シワの場所と風合いを潰さないかどうか」で判断することです。
| シワの状態 | ベストな対処 | プロの判断(なぜOK/NGか) |
|---|---|---|
| 軽いシワ(全体) | 霧吹き+手アイロン(手で伸ばす)で十分 | NG理由:麻独特のシャリ感やシボ(凹凸)を潰さないため。 |
| 強いシワ/衿元・裾 | 中温(140〜160℃)スチームなしで裏側からあて布をしてプレス | OK理由:衿や裾は清潔感が重要。麻は熱に強いため、部分的にシワを伸ばすのは有効。 |
| 全体のパリッと感を出したい | 完全乾燥前(8割乾き)に低〜中温で軽くアイロン | NGポイント:シボの強い織物(小千谷縮など)は凹凸がつぶれるため、アイロンを当てすぎないよう注意。 |
絹(絽・紗)の着物のお手入れと扱い方
絹の着物は、湿気や摩擦に弱く、とても繊細です。
正しいお手入れをすれば、光沢と風合いを長く保つことができます。
1. 洗濯は避ける
自宅での丸洗いはNG。シルク専用の洗剤を使い、
どうしても洗う場合は陰干しで自然乾燥させましょう。
直射日光は黄変(おうへん)の原因になります。
2. 着用後のブラッシング
やわらかい洋服ブラシで軽くホコリを払うだけでも十分なお手入れに。
摩擦が強いブラシは避け、優しくなでるのがコツです。
3. シミ抜きの基本
水やお茶など軽い汚れは、乾いた布でトントンと押さえるように除去。
油汚れや醤油などは無理せず専門店へ相談を。
4. 湿気対策
絹は湿気に弱いので、湿気取りシートや除湿剤を活用しましょう。
保管前には完全に乾いているか必ず確認を。
5. 防虫対策
防虫剤は着物に直接触れないよう、紙などに包んで使用します。
異なる種類を混ぜると化学反応で変色することがあるため注意。
💡ワンポイント
絹の着物は“すぐ洗う”より“その日のうちに乾かす”が鉄則。
軽い手入れを重ねることで、光沢と張りを長く保てます。
ポリエステルの着物のお手入れと扱い方
ポリエステルの着物は、丈夫でシワになりにくく、忙しい現代の暮らしにぴったりの素材です。
一方で、静電気や色落ちなど、特有の注意点もあります。
長所
軽くて丈夫、洗濯も簡単。速乾性が高く、型崩れしにくいのが魅力です。
注意点
高温に弱く、摩擦で毛羽立ちや毛玉ができることがあります。
また、洗濯時は色移りや静電気にも注意が必要です。
お手入れ方法
・洗濯:手洗いコースまたはネットに入れて弱水流で洗う。
・乾燥:日陰で自然乾燥。直射日光と乾燥機は避けましょう。
・アイロン:低温設定であて布を使用。高温はNG。
・収納:完全に乾かしてから、風通しのよい場所で保管します。
💡ワンポイント
静電気防止スプレーを使うと、着心地がぐっと快適に。
ポリエステルは扱い方ひとつで「普段着にも礼装にも」長く活躍してくれます。
夏着物を長持ちさせる!お手入れと保管のコツ

夏の着物を長く楽しむためには、着たあとのお手入れと保管が欠かせません。
汗や湿気をそのままにすると、生地の傷みや黄ばみ、カビの原因になることもあります。
とはいえ、しかっりとケアしておけば毎回クリーニングに出さなくても大丈夫なんです。
自宅でできる簡単なケアを習慣にするだけで、着物の美しさはぐんと長持ちします。
ここでは、夏着物を守るための基本的なお手入れと保管のコツをわかりやすく紹介します。
汗抜きケアで着物を守る!自宅でできる簡単メンテナンス
夏の着物はどうしても汗をかいてしまうもの。
でも、そのまま放置すると黄ばみ・カビ・繊維の劣化の原因になります。
毎回クリーニングに出すのは大変なので、まずは**自宅でできる“汗抜きケア”**を覚えておきましょう。
汗抜きのやり方(自宅でできる応急処置)
- 平らな場所に着物を広げ、汗がついた部分に霧吹きで軽く水をかけます。
- 柔らかいタオルを丸め、軽く押さえるようにトントンと叩きます。
- 1と2を繰り返して、繊維に残った塩分を抜きます。
- 輪ジミにならないよう、少し広めの範囲に霧吹きをしてぼかします。
- そのまま風通しの良い場所で自然乾燥させましょう。
- 最後に当て布をして軽くアイロンをかけると、シワも整って仕上がりがきれいです。
💡 ポイント
汗は乾くと見えなくなるため、「シワが取れにくい」「生地が重く感じる」部分は汗が残っているサインです。
特に襟元と脇のあたりは汗ジミが出やすいので、念入りにチェックしましょう。
湿気対策をしっかり行う
夏の着物に多い麻や絹などの天然素材は、湿気を吸いやすい性質があります。
日本の夏は高温多湿のため、放っておくとカビや変色の原因になることも。
保管する前には、完全に乾いていることを確認しましょう。
また、年に1〜2回は着物を出して風を通すことで湿気を防げます。
桐たんすや収納ケースを使う場合は、シリカゲルなどの乾燥剤入り除湿シートを併用するとより安心です。
虫食いから着物を守る予防策
着物を傷める最大の敵の一つが虫食いです。
湿度が60%を超える環境では虫の活動が活発になり、気づかないうちに大切な着物に小さな穴を開けてしまうことがあります。
長く美しく保つための基本は、何よりも「通気性を確保すること」です。
- 定期的な風通し: 定期的に着物をタンスや収納から出し、陰干しをして風を通しましょう。
- 収納場所の清掃: 引き出しや収納ケースの底にたまったホコリは、虫の温床になります。きれいに拭き取り、清潔に保ってください。
- 防虫剤の正しい使い方:
- 直に触れさせない: 防虫剤は、着物に直接触れないよう薄紙などに包んで配置するのが安全です。
- 種類は一つに統一: 異なる種類の防虫剤を混ぜて使うのは厳禁です。化学反応を起こし、大切な着物にシミや変色を引き起こすリスクがあるため、必ず一種類に絞ってご使用ください。
プロに任せる見極めポイント:素人判断はNG!の境界線

自宅でのケアでは落としきれない汚れや、見た目では判断しにくいトラブルもあります。
特に、以下のようなサインが見られる場合は、**「これ以上自分で触らない」**と決めて、早めに専門店へ相談しましょう。
- 汗や皮脂が染み込んだ部分(特に衿や袖口の裏側)
- シミやカビの初期症状(※小さな点状の薄い変色など)
【プロだけが知る見極めサイン】
見た目がきれいでも、繊維の奥に汗が残っていることがあります。
そのまま放置すると、生地が黄ばみやすく、後から修復が難しくなることも。
特に汗をかいた後、着物の「地風(じふう)」**が硬くなっている、あるいは「なんとなくゴワついている」と感じたら、それは繊維に汗の成分が残っているサインです。
着物のクリーニング店では、単なる「丸洗い」(※油性の汚れを落とすドライクリーニング)だけでなく、「汗抜き」(※水溶性の汚れを落とす処理)など、素材と汚れの種類に合わせた適切な処理が可能です。
大切な夏の着物を守るため、プロの目で見極めてもらいましょう。
まとめ:正しいお手入れで、夏の着物をもっと心地よく
夏の着物は、涼やかで軽やかな一方、汗や湿気に敏感な繊細な衣です。
だからこそ、着用したその日のケアと、季節を越えるための保管が大切になります。
麻は風合いを楽しみながら“ノーアイロン”で、
絹は湿気と摩擦を避けて“やさしくケア”、
ポリエステルは手軽さを生かして“清潔を保つ”──
それぞれの素材の特性を知ることで、着物はぐっと長持ちします。
着物を手入れする時間は、布と向き合う豊かなひととき。
少しの工夫で、あなたの一枚が何年も美しく輝き続けます。
✿コラム:Fumi’s Kimono Diary ✿
着付けの現場で夏の着物に触れていると、いつも思うことがあります。
それは、完璧さより“心地よさ”を優先することの大切さです。
汗をかいたり、少しシワが寄ったり──それは自然なこと。
大切なのは、その着物とどれだけ気持ちよく向き合えるかです。
麻のさらりとした肌ざわり、絹のほのかな光沢、ポリエステルの頼もしさ。
どの素材にも、季節とともに過ごす楽しみがあります。
一つ一つ素材の特徴を知って、夏の着物を楽しんでみてください♪