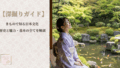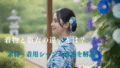着物の美しさを決めるのは、柄や色だけではありません。
実は「どんな糸で織られた生地か」が、着心地や耐久性、そして着姿の印象までも左右します。
私は日々、着付け師として数えきれない反物やお客様の着物に触れてきました。
その中で実感するのは、「見た目が似ていても、中身はまったく違う」ということ。
同じ絹でも、糸の種類や撚り、精練の仕方ひとつで、“滑りやすさ”“シワの出方”“保管のしやすさ”が変わります。
この記事では、そんな現場の経験をもとに、
素材・糸・風合いの見極め方を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
「知らずに失敗した」をなくし、長く愛せる一枚を選ぶための“生地を見極める目”を、一緒に育てていきましょう。
絹の常識を覆す!プロが教える「糸と繊維」の見極め方

「絹はどれも同じで、どれも高級」――そんなふうに思っていませんか?
実際には、絹にも性格のまったく違う2つの糸が存在します。
ひとつは、なめらかで光沢のある「長繊維(フィラメント糸)」、もうひとつは、ふっくらと柔らかい「短繊維(ステープル糸)」です。
着付け師として多くの生地に触れてきた中で、私はこの“糸の違い”こそが、着心地や着崩れのしやすさを左右する大きな要因だと実感しています。
見た目ではわからない「繊維の表情」に気づくと、着物選びの世界がぐっと広がります。
絹はすべて同じではない:光沢と毛羽立ちの真実
長繊維(フィラメント糸)
一本の繊維が長いのが長繊維(フィラメント糸)で、絹や化学繊維の代表格です。
一本の繭から長く引き出された糸をそのまま使うため、光沢があり、表面がなめらかです。
まるで水面のようなツヤを放ち、手触りはするりと滑るような感じです。
💡 着付け師のリアルな経験
このタイプの着物は、着付けのときの“滑り”が良すぎるのが最大の欠点です。
補正を入れずに着ると、動くたびに裾や衿が緩みやすく、着崩れの原因になります。
私はこの滑りを抑えるために、長繊維の着物特有の「滑りやすい箇所」に、いつも脱脂綿をカットして軽く仕込むという対策をしています。
具体的には、衿元や肩の丸みを出すために必要な場所です。
この簡単なひと手間で、着崩れのストレスから解放されます。
ちょっとした工夫ですが、これだけで着姿が安定し、見た目の印象も変わります。
短繊維(ステープル糸)
一本の繊維が短いのが短繊維(ステープル糸)で、綿やウール、紬などに使われるタイプです。
ふんわりとした温かみがあり、光沢よりも質感で魅せる生地です。
💡 着付け師のリアルな経験
短繊維の着物は吸湿性が高く、長時間でも蒸れにくい反面、保管時には虫食いリスクが格段に上がります。
私は自宅で綿やウール、紬の着物を補完するときは必ず湿気取りを入れ、年に二回は風通しを欠かしません。
ちょっとした手間で、長く美しい風合いを保てます。
見落としがちな化学繊維:実は最強の味方?
「化学繊維」と聞くと、どうしても“安価”“人工的”というイメージが先に立ちます。
けれど実際には、現代の化学繊維には絹に匹敵するほどの光沢と風合いをもつものも多く、
扱い方を知れば、着物ライフを支えてくれる頼もしい相棒になります。
代表的なのは、ポリエステル、レーヨンやアセテートといった再生・半合成繊維。
繊維の断面構造を調整することで、絹のような滑らかさやドレープ性を再現しています。
表面のツヤや手ざわりだけで見分けるのは難しく、多くの反物では「絹混」や「合繊交織」として登場します。
この見極めができるかどうかで、着物選びの精度がぐっと変わるのです。
ポリエステル
ポリエステルは、耐久性が高く、シワや水濡れに強い現代の着物ライフの最強の味方です。
比較的安価で、自宅で洗濯できる手軽さも魅力です。
しかし、長年、ポリエステル着物の着崩れに悩むお客様を数多く見てきました。
その最大の原因は、**「滑りやすさ」と「静電気」**です。
- 【プロの着崩れ対策】
- 滑り対策: 着崩れを防ぐために、小物で調整します。例えば、衿元の着崩れ防止のために「コーリンベルト」、紐を「モスリンの紐」、伊達巻を「滑り防止付のワンタッチの伊達巻」。完全とはいきませんが、ある程度は着崩れをふせげます。
- 静電気対策: 乾燥する季節の静電気は着物と肌襦袢が張り付く原因になります。静電気防止のスプレーなどを使用するといいと思います。
レーヨン(再生繊維)
レーヨンは、吸湿性があり、正絹に近い光沢感やしなやかなドレープ性が楽しめるため、価格以上の風合いを求める方に人気です。
しかし、水濡れにはプロでも最も神経を使う素材です。
【注意点と緊急対処法】
- 「水濡れで硬化・縮み」: レーヨンは水に濡れると繊維構造が崩れ、乾いた後にゴワゴワと硬化し、激しく縮む性質があります。通常のシミ抜きや洗濯では直せない致命的な失敗につながりやすいです。
- 緊急処置: 外出中にレーヨンの着物を濡らしてしまった場合、絶対に濡れた部分をゴシゴシと擦らないでください。白い(色物は色移りする恐れがあります)ハンカチや手ぬぐいを用意し、濡れた部分の着物をハンカチや手ぬぐいでさむように裏と表にあてて、軽くトントンと叩くようにしながら水分を含ませるように取っていきます。
㊟軽い水濡れの場合は速やかに応急処置をしておくと被害はほとんどありません。水滴が布にしみこんでしまった場合は応急処置をした後専門店にお任せしましょう。
アセテート(半合成繊維)・トリアセテート(半合成繊維)
アセテート
シルクに引けを取らない光沢と高級感を安価に手に入れられる魅力的な素材です
また、撥水性があるため、水濡れへの不安を軽減してくれる安心感もあります。
【着付け師の推奨と課題克服法】
- 課題:シワになりやすい アセテートの最大の課題は、着用中にシワになりやすいことです。このシワを回避するため、私は市販の「シワ防止スプレー」を外出前に使用しています。完璧とはいかないですが、ある程度防げます。これにより、高級感を保ちながら日常的に着用できます。
トリアセテート
アセテートの持つ高級感に加え、撥水性やなんといっても「しわになりにくい」といった実用性を向上させた素材です。
【使い分ける理由】
トリアセテートが優れているのは、**「シワになりにくい」という耐久性と、「冷感性」**を持つ快適性です。
- 夏場の着物として最適: 冷感性とさらりとした風合いが、着物特有の蒸れを軽減します。私が夏場の普段着や肌着の混紡されているものを推奨する際の、重要な判断基準の一つです。
- もし、しわが気になったら?: しわの気になる部分に当て布をし”低温(80℃~120℃程度の中温)”でアイロンをかけます。この時スチームアイロンは控えましょう。
繊維の種類と分類|天然と化学のちがい

実は、着物のお手入れの失敗の多くは、この「素材の違い」の根本的な誤解に起因しています。
繊維は、大きく天然繊維(絹や木綿など)と化学繊維(ポリエステルやレーヨンなど)の2つに分けられます。
この2つの違いは、単に「価格」や「風合い」だけではありません。
その主成分(化学構造)が根本的に異なるため、水や熱への反応がまるで逆になり、お手入れの難易度が決定的に変わってくるのです。
特に現代の着物ライフでは、**しわになりにくく、軽く丈夫な「化学繊維」をいかに味方につけるかがカギとなります。
ここでは、私が現場で扱う素材をベースに、天然と化学の持つ「個性」と、化学繊維の持つ「隠れた実力」**を分類と共に解説していきます。
天然繊維:自然から得られる繊維(動物・植物・鉱物が由来)
天然繊維の特徴
吸湿性や通気性に優れ、肌ざわりが良いなど着物素材として古くから使われています。四季の移り変わる日本の風土と、人の肌に最も馴染むように、古来より使われてきた繊維です。
天然繊維の種類
●動物繊維
天然繊維は、大きく分けて「動物繊維」と「植物繊維」があります。
動物がつくる繊維で、たんぱく質が主成分です。しなやかで保温性に優れているのが特徴です。
- 絹(シルク):家蚕(養蚕)や野蚕からとれる繭を利用した繊維。光沢が美しく、着物にもっとも多く用いられる高級素材です。
- 毛:羊毛(ウール)、カシミヤ、アルパカ、らくだ、アンゴラなど。やわらかさや暖かさに優れています。
| 素材 | 例 |
|---|---|
| 絹 | 家蚕(養蚕)、野蚕(天然) |
| 毛 | 羊毛、カシミア、アルパカ、らくだ、アンゴラ など |
●植物繊維
植物から得られる繊維で、セルロースが主成分です。通気性がよく、さらっとした肌触りが特徴です。
・種子毛繊維:綿花(コットン)、カポックなど。吸湿性に優れ、浴衣などに広く利用されます。
・靭皮繊維(じんぴせんい):苧麻(からむし)、黄麻(ジュート)、藤、芋麻、マニラ麻など。繊維自体にハリと強いコシ**があり、高級な夏の着物(上布など)や帯に用いられる、日本の夏には欠かせない素材です。
(⚠注意)麻全般(特に苧麻や亜麻)は、強いシワや水濡れ後の硬化(ゴワつき)に注意が必要です。
・果実繊維:椰子(ヤシ)など。
・その他:楮(こうぞ)、藺草(いぐさ)など。和紙や畳表の材料にもなります。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 種子毛 | 綿花、カポック |
| 靭皮繊維 | 苧麻、黄麻、藤、楮、芭蕉、マニラ麻 |
| 果実繊維 | 椰子(ヤシ) |
| その他 | 棕櫚(しゅろ)、藺草(いぐさ) |
※鉱物由来の繊維(例:石綿など)も存在しますが、着物や衣料用途には用いられていないため、本記事では省略しています。
化学繊維(人造繊維・合成繊維):化学的に加工・合成して作られた繊維
特徴
シワになりにくく、軽くて丈夫。お手入れがしやすく、現代の暮らしに合わせて発展してきました。
化学繊維の種類
化学繊維は、大きく「再生繊維」「半合成繊維」「合成繊維」の3つに分けられます。
それぞれに特徴があり、着物や帯の素材としても使われています。
💡 補足
最近は、天然繊維と化学繊維を組み合わせた**混紡(こんぼう)**の着物も増えています。混紡はそれぞれの長所を活かし、しわになりにくく耐久性があり、価格も抑えられるなどのメリットがあります。
●再生繊維(セルロース系)
木材パルプなど自然由来の原料を、いったん溶かしてから再び繊維にしたものです。光沢や手触りが絹に似ていることから「人工絹」と呼ばれることもあります。
例:レーヨン、キュプラ、ポリノジック
●半合成繊維
自然由来の成分(セルロースやタンパク質など)に化学処理を加えてつくられたものです。強度や発色性を高める工夫がされており、和装小物などに使われることもあります。
例:アセテート、トリアセテート、プロミックス
●合成繊維
石油や天然ガスなどを原料に、化学的に合成された完全な人工繊維です。軽くて丈夫、シワになりにくいといった特徴から、普段着の着物や裏地に広く利用されています。
例:ナイロン、ポリエステル、アクリル、ピニロン(クラレ・ユニチカ)
繊維と糸の基本|着物をカタチづくるもの

着物の生地は、天然繊維(絹や木綿)と化学繊維(ポリエステルやレーヨン)という、水や熱への反応が真逆の性質を持つ繊維でできています。
この「繊維」と、それを組み上げた「糸」の基本を知ることが、そして適切な手入れ方法を知るための鍵となります。
ここでは、繊維の製法や糸の太さといった裏側の知識をわかりやすく解説します。
糸の製法による分類|糸が生まれる3つの方法
糸は、どのようにつくられるかによって大きく3つに分けられます。
絹のように生糸をそのまま取り出すもの、化学繊維のように人工的につくり出すもの、
そして綿羊毛のように短い繊維を撚り合わせて糸にするものです。
| 分類名 | 説明 | 着物での例 |
|---|---|---|
| 製糸 | 生糸を取り出す(絹) | 小紋や訪問着、付け下げなどに使われる絹糸 |
| 紡糸 | 化学繊維をつくる製法 | ポリエステルの洗える着物、合繊の長襦袢 |
| 紡績 | 短繊維を撚って糸にする(綿・羊毛など) | 木綿の浴衣、ウールの普段着きもの |
さらに、着物ならではの魅力として 帯に金糸・銀糸を織り込む 例もあり、華やかさや格式を表現するのに欠かせません。
普段着の木綿やウールから、絹の礼装着物、そして格式高い帯まで──糸の種類と製法は、着物の姿かたちを左右し、私たちの装いを豊かに彩っています。
糸の太さの単位|生地の表情を左右する数字
糸には「太さ」を表すための単位があり、その違いが着物の生地感や風合いに大きく影響します。
| 単位 | 説明 | 着物でのイメージ |
|---|---|---|
| デニール(D) | 長繊維(フィラメント糸)の太さを表す単位。数値が大きいほど太くなります。 | ポリエステルの着物や長襦袢に使われる。太いと丈夫で張りがあり、細いとしなやか。 |
| 番手(S) | 紡績糸(綿や毛など)の太さを表す単位。数値が大きいほど細くなります。 | 木綿の浴衣やウールの着物に使われる。細番手はさらりと軽く、太番手は素朴でカジュアル。 |
💡ポイント
同じ「着物」でも、糸の太さによって生地の光沢や重さ、さらには着心地まで変わってきます。つまり、数字の違いはそのまま着物の表情の違いにつながっているのです。
撚糸(ねんし)について
糸はただ束ねただけではなく、「ねじり」を加えることで強さや質感を調整します。これを**撚糸(ねんし)**といいます。
撚糸には、ねじる方向や回数によって種類や特徴が生まれます。
- S撚り(右撚り):時計回り、S字に見える
- Z撚り(左撚り):反時計回り、Z字に見える
撚りの回数が多いほど糸は固くシャリ感が出て、少ないとふんわりと柔らかく仕上がります。
着物では、こうした撚糸の工夫が生地の風合いに大きく影響します。
| 撚りの強さ | 回数の目安(1mあたり) | 特徴 |
|---|---|---|
| あま撚り | 約300回以下 | 柔らかくふんわり(ガーゼなど) |
| 並撚り | 約1000回以下 | 一般的な撚り具合 |
| 強撚り | 約1000回以上 | 張りがありシャリ感が出る糸 |
使用例
- 強撚糸:夏着物や浴衣には、さらっとした涼感を出すためによく使われます。
- 撚糸:**紬(つむぎ)やお召(おめし)**には、独特の張りやしぼを出すために活かされています。
- あま撚り:ガーゼ風の裏地などには、柔らかさを引き出すために使用されることもあります。
このように、撚糸の加減ひとつで着物の表情や着心地が変わるのです。
●撚糸の種類
| 種類 | 説明 | 特徴・用途の例 |
|---|---|---|
| 片撚糸(かたよりいと) | 単糸1本〜数本を同じ方向に撚ったもの | 柔らかな布地を作りやすく、小紋や普段着の着物地に使われる |
| 諸撚糸(もよりいと) | 下撚り後、さらに数本をまとめて逆方向に再度撚ったもの(駒撚糸・壁撚糸など) | 強度が高くシャリ感や張りが出る。夏の着物(絽・紗など)や礼装用の帯地に多用される |
| その他 | 特殊な撚糸。駒撚糸(強撚でシャリ感)、壁撚り(均整の取れた強い撚り)、飾り撚り(意匠性を持たせた装飾的な撚り)など | 帯や高級生地、意匠性を重視した着物に使われることが多い |
※撚りの分類や撚り回数の目安は、一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター の情報を参考にしています。

※糸の撚り方で、風合いや用途が変わります。代表的な「S撚り」「Z撚り」の違いを図で確認しましょう。
精錬(せいれん)とは?
絹の原糸である「生糸(きいと)」には、
- フィブロイン(絹そのものの繊維)
- セリシン(フィブロインを包むタンパク質)
の二つが含まれています。
このセリシンなどの不純物を取り除く工程を 精練(せいれん) と呼びます。
精練によって絹は本来のやわらかさと美しい光沢を取り戻し、上質な風合いが生まれるのです。
●精練のタイミングによる分類
絹織物は、精練を行うタイミングによって次の2種類に分けられます
| 種類 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 先練織物(さきねりおりもの) | 糸を精練してから織る | 糸の光沢ややわらかさが活き、なめらかな仕上がりに |
| 後練織物(あとねりおりもの) | 織りあげてから精練する | 生地に張りが残り、織りの立体感を出しやすい |
着物ならではの例
- 先練:柔らかく光沢を重視した 縮緬や紋織の高級生地
- 後練:しっかりとした張りを残す 羽二重や袴地
高級織物では、この精練の方法が仕上がりを大きく左右するため、特に重要な工程とされています。
まとめ
着物の風合いや質感、そして機能性を左右するのは 「繊維」と「糸」 です。
素材の違いを知ることで、手入れの仕方やふさわしい着用シーンも見えてきます。
たとえば、柔らかな絹の小紋、丈夫な木綿の普段着、華やかに金糸を織り込んだ帯…。
糸や繊維の特徴を知れば、着物選びがもっと楽しくなるはずです。
織りや染めの基本を少しずつ学びながら、日本の織物文化を 「知って・触れて・楽しむ」 体験につなげてみてくださいね。
✿コラム:Fumi’s Kimono Diary ✿
先日、お気に入りの小紋を着てお出かけしたときのこと。
ふと袖を見ながら「この糸ってどっち巻きだろう…S撚り?Z撚り?」なんて考えてしまいました。
まわりから見れば「着物の世界にどっぷりな人」かもしれません(笑)。
実際のところ、S撚りかZ撚りかで普段の着心地が大きく変わるわけではありません。
でも、そんな小さな違いに目を向けると、着物がただの“服”じゃなくて、“物語のある布”に見えてくるんです。
糸一本にも歴史や工夫がつまっていて、それを知ることで着物との距離がちょっと近づく。
そんなささいな気づきが、私にとっては最高のご褒美なのです。