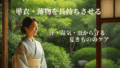七五三は、お子さまの健やかな成長を祝う大切な節目の行事です。
主役はお子さまですが、祖父母や兄弟姉妹の服装も、家族全体の調和や写真映えを左右する重要なポイントになります。
「祖母は着物を着てもマナー違反じゃない?」 「祖父はどんなスーツが無難で失敗しない?」 「兄弟姉妹はどんな服が写真に一番映えるの?」
この記事では、祖父母と兄弟のための服装マナーをNG例とおすすめスタイルを交えてわかりやすく解説します。
さらに、気になるお祝い金の相場や当日の役割まで、すべて解消できる「完全ガイド」です。
七五三の服装マナー:祖父母・兄弟が守るべき基本ルール

このパートでは、祖父母と兄弟姉妹が知っておきたい**「家族の調和」のポイントと、兄弟姉妹が和装をする際の「年齢による着こなしの作法」**について、基本的なマナーをご紹介します。
家族全体の調和:**「格を合わせる」**ことが最重要マナー
祖父母・兄弟姉妹を問わず、七五三の付き添い時の服装で最も重要なのは**「主役(お子さま)よりも目立たないこと」と「両親の服装と格を合わせること」**です。
| 関係者 | 守るべきルール | NGな例 |
|---|---|---|
| 祖父母 | 両親の服装の格(フォーマル度)に合わせる。両親が洋装なら洋装、和装なら和装で格を揃えると統一感が出ます。 | 両親がカジュアルな場合、祖父母だけが正礼装(モーニング、留袖など)で格が上がりすぎること。 |
| 兄弟姉妹 | 主役のお子さまを引き立てる服装を選ぶ。色や柄は落ち着いたものを選び、目立ちすぎないように配慮しましょう。 | 主役の子どもの衣装よりも派手な色や柄の服、極端にカジュアルな服(デニム、スウェットなど)。 |
写真映えのコツ:色調を統一して「家族の一体感」を出す
服装の色調を統一すると、集合写真にプロのような一体感が生まれます。
事前に家族で相談し、ネイビー、グレー、ベージュなどのベーシックカラーをベースにすると失敗がありません。
兄弟姉妹が和装をする際の「年齢による着こなしの慣習・決まり」
兄弟姉妹が和装をする場合は、伝統的な年齢による着こなしの慣習があります。
特に和装は年齢によって着られるものが異なるため、事前に確認しておきましょう。
| 兄弟姉妹 | 年齢 | 着用する和装の決まり |
|---|---|---|
| 男の子 | 5歳以上 | 大人と同じ紋付羽織袴がフォーマルな服装です。 |
| 4歳まで | 伝統的に「袴着の儀」を終えていないため、袴を着ることはできません(3歳で七五三を済ませた場合は可)。紐付きの着物に羽織を着用したスタイルになります。 | |
| 女の子 | 7歳以上 | 着物に帯を締める一般的なスタイルです。 |
| 6歳まで | 7歳未満の子ども用の着物は帯を締めるのが難しいため、着物に「被布(ひふ)」を羽織るスタイルが一般的です。 |
祖父母の服装【完全ガイド】NG例とおすすめスタイル

七五三におじいさま・おばあさまを招待する際は、事前に服装の相談をすることが必須です。
当日、ご家族のどなたか一人でも残念な思いをしないよう、両家間の格を揃えることを最優先しましょう。
【鉄則】祖父母の服装で守るべき「3つの調和」
- お子さまとの調和: お子さま(主役)が一番華やかになるよう、祖父母は格下の服装を選びましょう。
- ご両親との調和: 父親・母親の服装の**格とテイスト(和装/洋装)**を合わせましょう。
- 両家間の調和: 父方・母方、両家の祖父母の服装の格を統一しましょう。片方だけが普段着だと、もう片方が肩身の狭い思いをしてしまいます。
祖父母の洋装:おすすめスタイルとNG例
正式にはフォーマルかセミフォーマルですが、ご両親の服装と同格であれば問題ありません。
| 関係者 | おすすめスタイル | 【絶対NG】避けたい服装 |
|---|---|---|
| 祖父 | ダークカラーのスーツ(父親と同様)。お手持ちのスーツで問題ありません。ジャケットにスラックスなどのよそ行きのお出かけ着。 | Tシャツ、チノパン、ジーンズ、スニーカー。しわの入ったスラックスやよれよれのシャツなどの普段着。 |
| 祖母 | ワンピース、アンサンブルなどのよそ行きのおしゃれ着。**ジャケットとスカート(またはパンツ)**のセットアップ。 | 主役の子どもより目立つ派手な柄・色の服。カジュアルすぎる素材の服(Tシャツ、デニムなど)。 |
| 小物 | 靴はパンプスや革靴が基本。歩きやすいヒールなしや、歩き慣れた靴でも可。 | カジュアルすぎる靴(スニーカー、サンダルなど)。 |
祖父母の和装:格を意識した選び方
七五三のお参り参列者全員が和装で統一するのも素敵です。
和装で統一する場合も、主役のお子さま(正装)より格を一つ下げるのがマナーです。
例えばお子さまが羽織袴なら、祖父母は訪問着や色無地など一つ格下の着物を選びましょう
| 関係者 | 着用する和装(略礼装) | 格が上がりすぎるためNGな例 |
|---|---|---|
| 祖母 | 訪問着、色無地、付下げなどの外出用着物(略礼装)。 | 黒留袖(最上格の正礼装)など、お孫さまより格が高くなる着物。 |
| 祖父 | 紋なしの羽織袴。(洋装の場合) 格を合わせるためダークカラーのスーツを選びましょう。 |
祖父母の服装コーディネート例3選
写真にも残る大切な一日だからこそ、品格と華やかさを兼ね備えた服装選びが大切です。
和装・洋装それぞれの魅力を活かしたコーディネートで、お子様の成長を心からお祝いしましょう。
お祝いの席にふさわしい、上品で素敵な装いのヒントをご紹介します。



兄弟姉妹の服装【写真映え】NG例と年代別おすすめスタイル

七五三の付き添いをするごきょうだいの服装は、主役のお子さまを引き立てる「控えめなよそ行き」が基本です。
結婚式や入学式といった、改まった場で着るフォーマルな服装をイメージしましょう。
兄弟姉妹の服装「全体のマナーとNG例」
| NG例 | 理由と注意点 |
|---|---|
| カジュアルすぎる服装 | Tシャツ、デニム、スニーカーなどの日常着は、お祝いの特別感が薄れてしまいます。 |
| 主役より目立つ服 | 女の子の華美な発表会ドレスや、主役の子どもより鮮やかな色・柄の服は避けましょう。 |
| 靴 | 履き慣れた運動靴でも構いませんが、全身写真に靴まで写るため、服装に合ったローファーやフォーマルシューズを選ぶのがベストです。 |
【補足情報】
レンタル衣装の活用 写真スタジオで記念撮影をする場合は、付き添いの兄弟姉妹用のレンタル衣装が用意されていることがあります。撮影用か、お出かけ用かも含め、事前にスタジオに確認しておくとスムーズです。
兄弟姉妹の洋装:制服とフォーマルスタイル
制服がある学校の場合は、制服を着用するのが最も簡単でフォーマルです。
制服がない場合の男女別おすすめスタイルはこちらです。
| 関係者 | おすすめのフォーマルスタイル | カラー |
|---|---|---|
| 男の子 | スーツ、またはシャツとネクタイにズボン。暖かい時期はベストや半ズボン+ジャケットの組み合わせでも問題ありません。 | シックな黒、紺、グレー。 |
| 女の子 | ワンピースにジャケット、またはブラウスにスカートの組み合わせ。 | パステルカラー、白、シックな色など、落ち着いた色味。 |
兄弟姉妹の和装:年齢による着こなしの作法
ごきょうだい揃って和装にすると統一感があり、華やかになります。
ただし、和装には年齢による着こなしの慣習があります。
| 兄弟姉妹 | 年齢 | 着用する和装の慣習 |
|---|---|---|
| 男の子 | 5歳以上 | 大人と同じように紋付羽織袴がフォーマルな服装です。 |
| 4歳まで | 伝統的には「袴着の儀」を終えていないため、袴は着用しないのが一般的です(3歳で七五三を済ませた場合は可)。紐付きの着物に羽織を着用したスタイルになります。 | |
| 女の子 | 7歳以上 | 着物に帯を締める一般的なスタイルです。 |
| 6歳まで | 着物に「被布(ひふ)」を羽織るスタイルが一般的です。主役の子どもが引き立つよう、落ち着いた色味を選びましょう。 |
兄弟・姉妹の服装コーディネート例3選
写真に残る大切な一日だからこそ、兄弟姉妹の装いも心を込めて選びたいものです。
主役を引き立てながらも、上品で晴れの日にふさわしい服装にしてあげることで、ご家族みんなの思い出がより素敵になります。
和装でしたら落ち着いた色合いの着物、洋装でしたら清楚なワンピースやベストスタイルなどがおすすめです。
年齢に合わせた装いで揃えると、一緒にお祝いの雰囲気を楽しむことができます。
兄弟姉妹も安心して笑顔になれるような、素敵なコーディネートのヒントをご紹介します。



【Q&A】祖父母と兄弟のための疑問解消:お金・役割・その他のマナー

七五三の準備や当日の進行について、服装以外にも「お金」や「役割」に関する疑問は多いものです。
一般的なマナーや慣習をQ&A形式で解説します。
**Q1. 七五三のお祝い金(ご祝儀)の相場と渡し方のマナーは?**
| 項目 | お答えと心づかい |
| 一般的な相場 | 1万円〜3万円が目安です。 |
| 金額の判断基準 | 1万円程度:お祝い金のみを渡し、費用は両親が負担する場合。 |
| 3万円〜5万円程度:晴れ着や写真代、会食費用など、金銭的な負担を祖父母が一部または全て担う場合。 | |
| 考慮する点 | お祝い金とは別に着物などの贈り物をしているか、遠方からの交通費・宿泊費がかかっているかも考慮して調整します。 |
| 贈り方・マナー | **のし袋(祝儀袋)**に包んで手渡しするのがマナーです。 |
| 表書き | **「御祝」または「七五三御祝」**と書きます。 |
| 渡すタイミング | 七五三の参拝当日や、家族が集まる食事会の際など。新札を用意すると丁寧です。 |
**Q2. 七五三の写真代や食事会費用は誰が払うのが一般的なの?**
A. 一般的にはお子さまのご両親が払うのが基本です。
- 決まりはない: 写真代や食事代を誰が払うかについて、厳密な決まりやマナーは存在しません。
- 祖父母が払うケース: 地域や家系の風習、または「孫の成長を祝いたい」という祖父母の申し出により、祖父母が負担するケースもあります(かかる費用以上をお祝い金として渡す場合もあります)。
【最も重要な注意点】 後でトラブルにならないようにするためにも、費用負担については必ず事前にご両親と祖父母の間で話し合っておくことが大切です。
**Q3. 七五三に祖父母は参加すべき?参加の判断基準と両家への配慮は?**
A. 七五三に「必ず参加すべき」という決まりはありません。
ご両親からの招待や、ご家族の都合に合わせて判断するのが一般的です。
1. 参加の判断基準:無理のない状況か確認しましょう
| 参加するケース | 参加を辞退・見送るケース |
|---|---|
| 両家とも家が近いなど、アクセスに問題がない。 | 遠方に住んでいるため、長距離移動で体調に負担がかかる。 |
| ご両親から明確に招待があった。 | 体調不良や身内の不幸など、やむを得ない事情がある。 |
| 日取りや時間に無理がない。 | 交通費や宿泊費の負担が大きい。 |
2. 両家への配慮:「片方だけ」の参加に要注意
七五三はご家族だけで行うことも多いため、両家の祖父母を呼ぶ場合は日程やアクセスに余裕があるときに限られます。
- 両家で差をつけない: 父方・母方どちらかの祖父母を招待する場合、もう片方の祖父母にも声をかけるか、事前にご両親から丁寧な説明をしてもらうのが理想です。「どちらかを誘ってもう片方は誘わない」のは、祖父母間でわだかまりが生まれる原因になりかねません。
- 遠慮も大切: 両家の祖父母が集まると、ご両親が気疲れしてしまう可能性もあります。もし辞退や遠慮の意向がある場合は、無理に呼ばれるのを待たず、ご両親の意向を尊重しましょう。
【祖父母の心構え】 「呼ばなければならない」という決まりはないからこそ、ご両親の希望を最優先し、「行きたい」という気持ちと「ご両親に負担をかけたくない」という配慮のバランスを取ることが大切です。
**Q4. 七五三当日、祖父母が具体的にすることは何ですか?**
A. 祖父母は、当日の進行をスムーズにするための参加者であると同時に、サポート役としての役割も担います。
ご両親と協力し、お子さまの負担を軽減することを第一に考えましょう。
1. 当日の主な役割(参加・サポート)
- 神社・お寺への参拝とご祈祷への同行: お孫さんの健やかな成長を願う大切な行事です。ご両親と一緒にご祈祷を受けたり、お賽銭を入れて拝礼したりします。
- 記念写真撮影への参加: 集合写真の際は一緒に写ることで、家族の良い記念になります。お子さまが疲れないよう、撮影時の補助や見守り役を担うこともあります。
- お祝いの食事会への参加: 家族と祖父母が揃って食事会を開くのが一般的です。レストランやご家庭での食事会に参加し、お祝いムードを盛り上げます。
2. 事前の準備と心構え(配慮事項)
| 項目 | 祖父母が配慮すべきこと |
|---|---|
| 日程調整・相談 | お参りや食事会の場所、日程、写真撮影の有無など、ご両親の予定に合わせて調整しましょう。事前に両家で相談し、情報を共有することが大切です。 |
| お子さまの負担への配慮 | 七五三の行事を一日で全て済ませようとすると、お子さまは疲れてしまいます。前撮り/後撮りを利用するなど、無理のないスケジュールになっているか確認し、当日も休憩を促すなど配慮しましょう。 |
| 服装の最終確認 | 事前にご両親と相談した服装(洋装または和装)を再度確認し、上品で華やかな装いで臨みましょう。 |
まとめ:マナーは「心づかい」、大切なのは家族の笑顔
七五三の祖父母・兄弟姉妹の服装は、「主役であるお子さまを引き立てる」というマナーと、「家族全員の調和」が最も大切です。
この記事で解説した通り、祖父母はご両親の服装の格に合わせ、兄弟姉妹は華美になりすぎないよう控えめなよそ行きを選びましょう。
和装の際の年齢による着こなしの作法や、お祝い金の相場と心づかいまで、事前にご家族で確認しておくことが、当日をスムーズに迎える鍵となります。
服装マナーは、お互いを思いやる心づかいです。
準備の段階からご家族でよく相談し、七五三という佳き日が、ご家族皆様にとって笑顔あふれる最高の思い出となることを願っています。
✿ コラム:Fumi’s Kimono Diary ✿
昨年、姪の七五三に同行したときのこと。
慣れない着物に少し緊張していた姪が、祖母に手を添えてもらった瞬間、表情がふっと和らぎました。
主役は子どもですが、その周りで支える祖父母や兄弟姉妹の存在があってこそ、安心して笑顔になれるのだと感じました。
写真を見返すたびに思うのは、豪華な衣装よりも、そばで見守る温かな眼差しこそが一番の思い出になるということです。