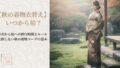秋は、着物好きにとって一番心が躍る季節です。
紅葉や月、秋の草花など、日本の四季の中でも特に情緒あふれる美しい文様がたくさんあるからです。
でも、着物を着始めたばかりの頃は、こんな風に悩みませんか?
「桜の柄は春だけど、菊や紅葉はいつから着ていいの?」 「9月の残暑に、秋の柄を着てもおかしくない?」
着物の世界には「季節の先取り」という素敵な習慣がありますが、具体的なタイミングは少し難しいですよね。
この記事では、9月・10月・11月それぞれの時期にふさわしい「秋の文様」と、その「意味」を分かりやすくまとめました。
秋の着物に映える!代表的な2つの「秋文様」
着物を華やかに彩る「文様」には、日本人が古くから大切にしてきた願いや暮らしのしきたり、
そして四季を愛でる心が表現されています。
とくに草花や風景を描いた「植物文様」や「風景文様」は身近で親しまれてきました。
まずは、秋の着物といえばこれ!という代表的な2つのスタイルをご紹介します。
1. 秋草文様(あきくさもんよう)
〜夏の終わりから着られる、涼しさを呼ぶ柄〜
「秋草文様」とは、秋の野に咲く草花をモチーフにした文様です。 具体的には、「秋の七草(萩・尾花・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗)」に、菊や竜胆(りんどう)などを加えて描かれます。
【ここがポイント!】 「秋」という名前がついていますが、実は夏(7月・8月)の終わりから9月にかけて着るのが最も粋とされています。 残暑が厳しい時期に、着物の柄で「もうすぐ秋が来ますよ」と涼しさを演出する。日本人の奥ゆかしい「おもてなしの心」が込められた文様なのです。
| 文様 | 特徴・意味 | 着物での表現 |
|---|---|---|
 桔梗(ききょう) 桔梗(ききょう) | 紫色と星形の花びらが印象的。ふくらんだつぼみも美しい。 | 尾形光琳も愛した花で、格調ある意匠として人気。 |
 萩(はぎ) 萩(はぎ) | 夏の終わりに赤紫や白の小花を咲かせる。漢字に「秋」を含む。 | 万葉集で最も多く詠まれた花。秋草文様の代表格。 |
 女郎花(おみなえし) 女郎花(おみなえし) | 淡黄色の小花を傘状につける多年草。すらりとした姿。 | 「思い草」とも呼ばれ、歌に多く登場。他の草花とともに描かれることが多い。 |
 撫子(なでしこ) 撫子(なでしこ) | 薄紅色の細かく裂けた花びらが可憐。名は「撫でたくなるほど愛らしい」から。 | 「大和撫子」という言葉通り、女性らしさを象徴。小紋などに多く用いられる。 |
 葛(くず) 葛(くず) | ツル性植物で紫や白の花を咲かせる。繊維や薬、和菓子にも利用。 | 暮らしに根付いた植物を意匠化。素朴で温かみのある柄。 |
 芒(すすき) 芒(すすき) | 古くから神聖視され、魔除けとしても用いられる。中秋の名月の象徴。 | 曲線美を生かした優美な文様。家紋や秋の夜長を描く意匠に多い。 |
 藤袴(ふじばかま) 藤袴(ふじばかま) | 秋に淡紫色の小花を多数つける。花形が袴に似ることから命名。 | 平安時代には乾燥させ香り袋にし、十二単に忍ばせた。 |
2. 吹き寄せ文様(ふきよせもんよう)
〜秋の深まりを感じさせる風景画〜
「吹き寄せ」とは、風で木ごの葉や木の実がクルクルと舞い、ひとところに集まった様子を描いた風情ある文様です。 紅葉(もみじ)、松葉、銀杏(いちょう)、松ぼっくりなどがカラフルに描かれます。
【意味と願い】 落ち葉が集まる様子は**「富貴寄(ふきよせ)=良いものが集まる」**に通じるとされ、実はとても縁起の良い柄です。 色とりどりの落ち葉は、着ているだけで秋の景色を身にまとっているような華やかさがあります。
| 文様 | 特徴・意味 | 着物での表現 |
|---|---|---|
 紅葉(もみじ) 紅葉(もみじ) | 長寿・幸運・世渡り上手を象徴。 | 秋の象徴文様。桃山時代から多く描かれた伝統柄。 |
 松葉 松葉 | 夫婦円満・縁起を象徴。 | 落ち葉になっても根元で繋がるため、仲睦まじさを表す。 |
 松毬(まつかさ) 松毬(まつかさ) | 豊かさ・縁起を象徴。 | 個性的なフォルムで存在感があり、家紋にも用いられる。 |
 銀杏(いちょう) 銀杏(いちょう) | 神仏加護・生命力・開運を象徴。 | ご神木とされ、長寿・火に強い木として繁栄を表す。 |
 蔦(つた) 蔦(つた) | 繁栄・生命力を象徴。 | 力強く伸びる姿が繁栄を表し、葉の色で季節感を演出。 |
 栗の実 栗の実 | 豊穣・勝運・金運を象徴。 | 「勝ち栗」で武士の縁起担ぎに。栗きんとんは財宝に通じる色。 |
【月別】9月・10月・11月のおすすめ文様と選び方
ここからは、月ごとの「旬」な柄をご紹介します。
「今の時期、何を着よう?」と迷った時の参考にしてください。
9月:お月見と秋草で「涼」を演出
9月はまだ暑さが残りますが、暦の上では秋。
中秋の名月(十五夜)があるこの時期は、夜空や月をイメージさせる柄がおしゃれです。
 兎文様
兎文様
月と組み合わされることが多い縁起柄。中秋の名月(8月後半〜9月)にぴったりで、兎だけを意匠化したものは通年着用が可能です。
 月文様
月文様
太陽と並び古くから信仰の対象とされ、吉祥文様として親しまれます。兎や秋草と組み合わせると秋らしさが際立ちます。
 秋草文様
秋草文様
桔梗・萩・女郎花・撫子・葛・芒・藤袴を描いた柄。蝶や鹿と組み合わせられることもあり、夏から初秋に涼しさを先取りできる定番柄です。
 桔梗
桔梗
紫の星形の花で、秋の七草のひとつ。残暑(8月〜9月初旬)に着るのが似合います。他の秋草や女郎花と組み合わせられることが多いです。
 萩
萩
秋を代表する花で「鹿鳴草」とも呼ばれます。鹿との取り合わせは古典的で、秋草文様の中心モチーフです。
 女郎花
女郎花
淡黄色の小花をつける多年草。7月〜10月に咲き、夏から秋にかけての着用に適します。桔梗や萩と一緒に描かれることが多いです。
 撫子
撫子
可憐な花姿で「大和撫子」の象徴。8〜9月の残暑に着ることで秋を先取りできます。秋草や蝶と合わせて使われることもあります。
 葛
葛
強い生命力を象徴するつる草。秋草文様の一部として用いられ、桔梗や萩などと組み合わせて描かれます。
 竜胆
竜胆
紫の鐘形の花で、強さを表す秋の草花。9月に見頃を迎え、菊や桔梗と組み合わされることもあります。
 柘榴(ざくろ)
柘榴(ざくろ)
子孫繁栄を象徴する果実。写実的に描かれたものは9〜10月頃に、デザイン化されたものは通年着用が可能です。
 葡萄
葡萄
豊穣・子孫繁栄の象徴。写実的な葡萄は秋に、唐草と組み合わせた葡萄唐草は通年着用できる古典文様です。
 吹き寄せ
吹き寄せ
木の葉や草花が風に吹き寄せられて散り集まる様子を表した文様。秋草や紅葉をはじめ、桜・笹・四季草花・梅などさまざまな植物と組み合わせて描かれることも多く、通年着用できる柄です。
💡 ワンポイント・アドバイス :いきなり着物の柄で取り入れるのが難しい場合は、「帯留め」や「半衿」などの小物でうさぎや月を取り入れてみましょう。さりげない季節感が、着物慣れした雰囲気を醸し出します。
9月の着こなしをもっと詳しく: 「まだ暑い?もう秋?」気温選びが一番難しいのが9月です。 「何℃になったら単衣(ひとえ)にする?」「薄物はいつまで?」 そんな迷いやすい9月の着物ルールと、気温別の正解コーデはこちらで詳しく解説しています。
10月:景色に映える!秋の深まりを楽しむ優美な花々
10月は秋の盛りを象徴する花や果実、紅葉の先取り文様がふさわしい季節です。
 柘榴(ざくろ)
柘榴(ざくろ)
子孫繁栄を象徴する果実。写実的に描かれたものは9〜10月頃に、デザイン化されたものは通年着用が可能です。
 葡萄
葡萄
豊穣・子孫繁栄の象徴。写実的な葡萄は秋に、唐草と組み合わせた葡萄唐草は通年着用できる古典文様です。
 菊(注)
菊(注)
長寿や繁栄を象徴し、重陽の節句にも用いられた花。写実的な菊は10〜11月頃に着るのがふさわしく、デザイン化されたものは通年用いられます
 紅葉(もみじ)
紅葉(もみじ)
秋を代表する文様。見頃は11月末だが、10月に先取りして着るのが粋。流水と組み合わせた「竜田川」、桜と紅葉を合わせた「桜楓」、青々とした楓と紅葉を一緒に描いた意匠などがあり、桜楓は通年用いられる。
10月の着こなしをもっと詳しく :もっと具体的なコーディネート実例を見たい方は、こちらの記事も参考にしてください。
11月:紅葉(もみじ)と実りで秋を締めくくる
寒さを感じ始める11月は、暖かみのある色や、晩秋の景色を楽しみましょう。
 菊(注)
菊(注)
長寿や繁栄を象徴し、重陽の節句にも用いられた花。写実的な菊は10〜11月頃に着るのがふさわしく、デザイン化されたものは通年用いられます。
 紅葉(もみじ)
紅葉(もみじ)
秋を代表する柄で、11月の盛りに最も映えます。流水と合わせた「竜田川」、桜と組み合わせた「桜楓」、青楓と共に描かれる意匠など、バリエーションも豊富です。
 竜田川
竜田川
紅葉と流水を組み合わせた古典的な意匠で、秋の深まりを象徴します。紅葉文様の中でも特に11月にふさわしいデザインです。
(注)菊文様
菊は中国から奈良〜平安時代に伝わり、鎌倉時代には広く愛好されました。長寿を象徴する花で、菊水・菊慈童といった延命伝説に由来します。陰暦9月9日の「重陽の節句(菊の節句)」では、菊の花を浮かべた酒や菊の被綿が邪気を払うとされ、長寿を願う行事が行われました。現在も皇室の御紋として広く知られています。
着物の文様としては種類が豊富で、以下のようなバリエーションがあります。
- 狢菊(むじなぎく) … 小さな花びらを密に描いた柄。江戸小紋や浴衣に多用。
- 菊の丸 … 菊を丸形にデザイン化。松・梅・桜など他の「花の丸」との組み合わせも多い。
- 乱菊 … 長い花びらが乱れて咲く姿を大胆に表現。華やかで迫力あるデザイン。
- 菊水 … 菊と流水を組み合わせた吉祥柄。延命長寿を象徴し、家紋にも使われる。
11月の着こなしをもっと詳しく :晩秋の寒さ対策や、季節の変わり目のコーディネートはこちらの記事で解説しています。
秋の模様と着物の格の関係


礼装(訪問着)
ベージュ地に末広を配し、菊・桔梗・萩・紅葉・女郎花など秋の草花をあしらった、やわらかな印象の訪問着です。おさえた朱色の袋帯には菊や竹、鳳凰などの吉祥文様が添えられ、季節感と格調を兼ね備えています。結婚式やお茶会、観劇や食事会など、改まった場にふさわしい装いです。
🍂 格の高い文様



菊
竜田川
吹き寄せ


紅葉
秋草


江戸小紋
紅葉にちなんだコーディネート。薄ピンクの江戸小紋は、細かな地紋が上品で略礼装としても通用します。白地に紅葉が描かれた名古屋帯を合わせることで、秋の彩りと季節感が加わり、軽いお茶会や観劇などにもふさわしい装いとなります。
🟪 江戸小紋 × 略礼装向きの文様



菊
紅葉
竜田川


秋草
吹き寄せ
🟨 江戸小紋 × 普段着向きの文様



銀杏
兎
お月見


小紋(普段着)
撫子色地に辻が花模様のおしゃれな小紋です。華やかな柄ゆきながらもカジュアル感があり、街歩きや食事会など気軽な場にぴったりの装いとなります。帯や小物次第で、季節感や個性を楽しめるのも小紋ならではの魅力です。
🟡普段着向き



銀杏
ザクロ
栗の実



撫子
お月見
兎
まとめ:季節の柄を知れば、着物はもっと楽しくなる
「この柄、なんていう意味だろう?」「今の季節に着ていいのかな?」
そうやって少し立ち止まって考える時間こそが、着物を着る醍醐味(だいごみ)かもしれません。
- 9月は、月とうさぎで遊び心を。
- 10月は、菊で格調高く。
- 11月は、紅葉や吹き寄せで季節の移ろいを。
ぜひ、今の季節にぴったりの柄を見つけて、秋のお出かけを楽しんでくださいね。
お気に入りの柄を身にまとうと、いつもの街歩きがもっと特別なものになりますよ。