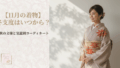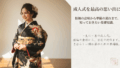着物で結婚式に参列されるのは、とても素敵で華やかなことです。
しかし、「どんな着物を選べばいいの?」「必要な小物は?」「マナーは?」と不安を感じる初心者の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では立場に合わせた最適な着物の選び方と、当日を心から楽しむための準備をわかりやすくお伝えします。
あなたが選んだ一枚で、自信をもって最高の笑顔で祝福できますように!
結婚式にふさわしい着物の基本的な説明と特徴

結婚式というお祝いの席では、洋装と同様に「格(かく)」の高い着物を選びます。
着物の格とは、フォーマル度合いを示すもので、最も格が高いのが「正礼装(せいれいそう)」、それに次ぐのが「準礼装(じゅんれいそう)」、「略礼装(りゃくれいそう)」となります。
主に結婚式で着用される代表的な着物をご紹介します。

黒留袖
格 正礼装
特徴 地色が黒。染め抜の五つ紋が入る。
誰が着る? 新郎新婦の母親、既婚の近しい親族

色留袖
格 正礼装~準礼装
特徴 地色が色物。既婚・未婚問わず着用可。紋の数(五つ紋・三つ紋・一つ紋)で格が変わる。
誰が着る? 新郎新婦の姉妹、親族、主賓など

振袖
格 正礼装
特徴 未婚女性の第一礼装。
誰が着る? 新郎新婦の未婚の姉妹、未婚の友人・同僚

訪問着
格 準礼装
特徴 模様が肩から裾、袖などに渡って繋がる「絵羽模様」が特徴。未婚・既婚問わず着用可。
誰が着る? 友人、同僚、上司、親族(色留袖に準じる立場)

付け下げ
格 略礼装
特徴 付け下げは、訪問着に次ぐ準礼装の着物。縫い目をまたいで柄がつながらず、控えめで上品な雰囲気が特徴。フォーマルからセミフォーマルまで幅広い場面で着用可。
誰が着る? 友人、同僚など

色無地
格 略礼装
特徴 黒以外の色一色で、柄がない。一つ紋以上で結婚式にも着用可能。
誰が着る? 友人、同僚、控えめな装いを好む方
結婚式にふさわしい立場別の着物の具体的な選び方

着物選びは、「新郎新婦との関係性」「ご自身の年齢・既婚/未婚」が鍵となります。
主役である花嫁よりも目立つ装いは避け、「格の配慮」を心がけ、お祝いの気持ちを表しましょう。
親族の着物選び
親族は「ゲストをお迎えする側」として、最も格の高い正礼装(黒留袖・振袖)やそれに準じる着物を着用するのが一般的です。
1. 新郎新婦の母親・既婚の祖母・伯母・叔母
着物:黒留袖(くろとめそで)
選び方のポイント: 既婚女性の最高礼装である五つ紋のものを着用します。
柄は鶴や松竹梅など、おめでたい吉祥文様を選びましょう。他の親族は、新郎新婦の母親よりもやや柄が控えめなものを選ぶと、立場への配慮が伝わります。
2. 新郎新婦の未婚の姉妹・伯母・叔母
着物:振袖 または 色留袖(いろとめそで)
選び方のポイント: 振袖の場合、花嫁の着物(大振袖)より袖丈が短い中振袖や、柄が控えめなものを選び、花嫁の格を立てる配慮が必要です。
色留袖の場合は、親族として三つ紋または五つ紋を選びます。
ゲストの着物選び
友人や同僚などゲストは、**準礼装(訪問着、色留袖)や略礼装(付下げ、色無地など)**を選び、控えめな華やかさを意識します。
1. 未婚の友人・同僚
着物:振袖 または 訪問着(ほうもんぎ)、付下げ(つけさげ)
選び方のポイント: 振袖は華やかで未婚の方に最適です。
30代以上で振袖を着る場合は、シックな地色で落ち着いた雰囲気のものを選ぶと上品です。
訪問着や付下げも、明るく華やかな色柄を選び、お祝いの場にふさわしい装いにしましょう。
2. 既婚の友人・同僚・上司
着物:訪問着、色留袖(一つ紋・三つ紋)、付下げ、色無地(一つ紋・三つ紋)
訪問着/付下げのポイント: 既婚女性の準礼装として最も一般的です。
年代に合った品のある色柄を選びます。
付下げは訪問着よりも控えめな装いを好む方に適しています。
💡【補足】上司・主賓としての参列: 祝辞を読まれるなど、特に格が求められる上司や主賓の方は、訪問着や一つ紋・三つ紋の色留袖など、略礼装の中でも格調の高い着物を選ぶことをおすすめします。信頼感のある品格と華やかさのバランスを意識しましょう。
結婚式にふさわしい立場別の着物選びの注意点

着物選びには、洋装とは異なる配慮が必要です。以下の点に特に注意してください。
1. 避けるべき色と柄
色について
白: 花嫁の色と被るため、着物・帯・小物全てにおいて白一色の装いは避けてください。
黒: 親族の正装である黒留袖と紛らわしいため、ゲストとして黒地の着物は避けたほうが無難です。
柄について
| 柄 | 避けた方がよいとされる理由 |
| 桜 | 早く「散る」ことを連想させる |
| 椿 | 花が丸ごと「落ちる」(首が落ちるイメージ)を連想させる |
| 下り藤 | 「下がる」ことを連想させる |
| 梅 | 花びらを「こぼす」(散る)と表現されることがある |
| 蝶 | 「浮気」や「移り気」といった意味で気にされることがある |
問題ないとされるケース
- 他の縁起の良い柄と一緒に描かれている場合(例:松竹梅と一緒の梅、花と一緒に描かれた蝶)。
- その柄をモチーフにした抽象的なデザインの場合。
避けた方が無難なのは?
- 上記の柄が単体で大きくメインに描かれているもの。
- 写実的に、「散りゆく様子」(例:桜吹雪)などが描かれているもの。
【最終確認】 もし手持ちの着物に気になる柄がメインで入っている場合は、事前に新郎新婦に相談することをおすすめします。
2. 花嫁より目立たないようにする
- 新婦の衣装(特に色や柄)と被らないように配慮しましょう。花嫁よりも格上になったり、派手過ぎる装いになったりしないよう、意識して控えめな華やかさに留めます。
3. 季節感の配慮
- 夏の着物: 7月・8月は、透け感のある夏用の着物(絽(ろ)や紗(しゃ))を着用するのがマナーです。
着付けのために必要な準備物リスト

着物本体、帯、帯揚げ、帯締め、草履、バッグのほかに、着付けのために必ず必要な小物があります。
| カテゴリ | 必要なもの | レンタル/自前の注意点 |
| 【必須】肌着 | 1. 肌襦袢(はだじゅばん) / 裾除け(すそよけ) | レンタルでも多くの場合、ご自身で準備が必要です。 |
| 2. 足袋(たび) | 必ず白色のものを。衛生上、レンタルでも買取または自己準備が多いです。 | |
| 【必須】補正 | 3. 補正用タオル | 体型を筒型にするための補正。薄手のタオル数枚(3~5枚程度)。レンタルであっても必ずご自身でご用意ください。 |
| 【着付け】基本小物 | 4. 長襦袢(ながじゅばん) / 半襟 / 襟芯 | **レンタルの場合はセットに含まれます。**自前の場合、長襦袢に半襟が縫い付けてあるか確認が必要です。 |
| 5. 腰紐(こしひも) / 伊達締め(だてじめ) | 着物を固定する紐類。腰紐は4~5本、伊達締めは2本あると安心。レンタルの場合はセットに含まれます。 | |
| 6. 帯板(おびいた) / 帯枕(おびまくら) | 帯の形を整える小物。レンタルの場合はセットに含まれます。 | |
| 7. 帯締め / 帯揚げ | 帯周りを飾る小物。金銀の入った礼装用。レンタルの場合はセットに含まれます。 | |
| 【その他】 | 8. 末広(すえひろ) | 扇子。黒塗りの骨に金銀の地紙など、礼装用のもの。 |
結婚式での着物のマナー

1. 殺生を連想させる小物は避ける
小物(素材)
バッグや草履の素材は、革製品やファー(毛皮)など、殺生を連想させるものは 避けてください。絹や布製、エナメルなど、上品なものを選びましょう。
2. 美しい着姿を保つプロの秘訣
補正の極意:
補正用タオルは、ウエストのくぼみや胸の下など、凹んだ部分を埋めて「寸胴(ずんどう)体型」にすることが目的です。これにより、着物が体にフィットし、着崩れを防げます。
腰紐の締める位置:
腰紐は、腰骨の少し上、一番くびれた部分を避けて締めるのがコツです。これにより、苦しくなく、着崩れにくい状態が作れます。
3. 季節・天候に合わせた快適な過ごし方
冬場の防寒対策:
- インナーの裏技: 防寒インナー(例:ヒートテックなど)を着用する際、襟ぐりの後ろ側が着物の襟(衣紋)から見えてしまうのを防ぐため、インナーを前後逆に着るのがおすすめです。後身頃の襟ぐりが広くなり、衣紋を深く抜いてもインナーが見えません。
- スパッツの活用: 着物の裾さばきを良くし、防寒にもなるひざ丈のスパッツを着用すると、冬場の移動も快適です。
夏場の汗対策:
- 肌襦袢と裾除けの下に、吸水性・速乾性のある和装用インナーをさらに着用すると、汗による貼りつきや不快感を軽減できます。
まとめ:喜びと自信をもって結婚式に参列するために
着物で結婚式に参列することは、新郎新婦にとって心からのお祝いの気持ちが伝わる、とても素敵な贈り物です。
あなたにとって最高の一着を選び、プロの秘訣を参考にしっかり準備を整えれば、当日は自信をもって振る舞うことができ、着物を選んだ喜びを存分に感じていただけるでしょう。
この記事が、あなたの特別な一日を華やかに彩る一助となれば幸いです。