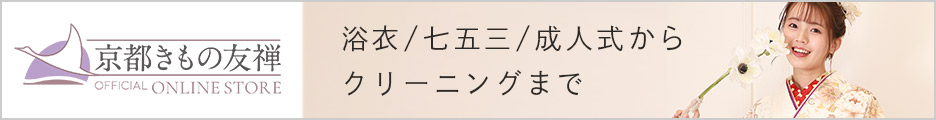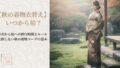[PR]
お子さんがそろそろ七五三の時期を迎えるころになると、「そういえば七五三ってどういう行事だったかな?」と疑問に思う方も少なくありません。
昔から大切にされてきた行事だけれど、実際の由来や歴史については意外と知られていないものです。
今さら人には聞きにくいけれど、やっぱり知っておきたい――そんな方に向けて、七五三の意味や起源、11月15日とされる理由、そして現代の祝い方までをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、七五三の背景がぐっと身近に感じられ、お参りや写真撮影がいっそう特別な時間になるはずです。
七五三とは

七五三(しちごさん)とは、日本に古くから伝わる子どもの成長を祝う伝統行事のひとつです。
一般的には三歳の女の子、五歳の男の子、七歳の女の子が11月15日に神社へお参りをして、
これでの成長を感謝し、これからの健やかな成長を祈ります。
近年では、男の子も三歳でお祝いをすることが増えてきました。
また参拝の時期も11月15日に限らず、9月から11月の吉日や土日祝日に行うご家庭が多くなっています。
地域や家庭によっては、五歳の女の子や七歳の男の子もお祝いを行うことがあります。
ご祈祷を受ける神社は本来は地元の氏神様ですが、大きな神社や有名な神社を選ぶ方も少なくありません。
また、こうした伝統に合わせてキリスト教の教会でも七五三のお祝いが行われることがあります。
七五三の歴史・由来

七五三の起源は平安時代の通過儀礼にあり、子どもの成長の節目を祝う三つの儀式「髪置き」「袴着」「帯解き」がもとになっています。
江戸時代には将軍・徳川綱吉が三歳になった長男・徳松君の成長を願って「髪置きの儀」を行い、その日が11月15日だったことから、七五三のお祝いが武家社会から庶民へと広まりました。
昔は「七歳までは神のうち」といわれるほど、子どもの命は不安定なものでした。
だからこそ、節目ごとの儀式はとても大切にされ、現代では祝い着と結びついて華やかな伝統行事として受け継がれています。
三歳(男女):髪置き(かみおき)
由来
平安時代には、生後七日目に髪を剃り、三歳までは丸坊主で育てる風習がありました。これは病気を防ぎ、健やかな髪の成長を願ったためです。三歳になると「髪置きの儀」を行い、白糸や綿を頭に置いて長寿を祈願しました。
服装
女の子は「三つ身(みつみ)」と呼ばれる小さな着物に「被布(ひふ)」を羽織るのが一般的です。帯を使わず紐で結ぶだけなので、着崩れしにくく動きやすい装いです。男の子は羽織袴を着る場合もありますが、近年は女の子と同じ被布スタイルを選ぶ家庭も増えています。五歳で羽織袴を着る予定なら、三歳は被布で子どもらしい可愛らしさを残すのも素敵です。


▶ 3歳の七五三についてはこちらで詳しく解説しています
五歳(男児):袴着(はかまぎ)
由来
五歳の男の子は「袴着(はかまぎ)の儀」を迎えます。初めて袴を身に着け、碁盤の上に立たせて「四方を制す」と願いを込めたと伝えられています。この節目を経て、男の子は少年として認められるようになりました。
服装
伝統的には「羽織袴(はおりはかま)」を着用します。羽織には鷹や兜など勇ましい柄が選ばれることが多く、袴には短剣や末広(扇子)を合わせます。凛々しく堂々とした姿は七五三ならではの晴れ姿です。

▶ 5歳の七五三についてはこちらで詳しく解説しています
七歳(女児):帯解き(おびとき)
由来
七歳になると、子ども用の紐付きの着物を卒業し、大人と同じ帯を締める「帯解き(紐解き)」を迎えました。
それまでは女児は付け紐のついた着物を着ていましたが、この年齢からはそれをやめ、本式の帯を締める着物に切り替えます。
これを「紐解き」「帯解き」と呼び、一人前として扱われる大切な節目とされてきました。
服装
七歳の女の子は「四つ身(よつみ)」と呼ばれる子どもサイズの本格的な着物を着ます。
帯は結びやすい「作り帯」が主流で、筥迫(はこせこ)や扇子、草履、髪飾りなどを揃えて華やかに仕上げます。
帯解きにふさわしい装いで、子どもらしさの中にも大人びた雰囲気が漂います。

▶ 7歳の七五三についてはこちらで詳しく解説しています
昔は子どもの死亡率が高く、「七歳までは神の子」といわれるほど命は不確かでした。
そのため七歳を迎えることは大きな意味を持ち、社会的にも精神的にも一人前として扱われるようになったのです。
親の服装|子どもの晴れ姿を引き立てる選び方
【PR】「家族全員で着物」を叶える!高品質着物レンタルで親の服装も安心
お子様の七五三は、ご家族の思い出にもなる大切な日。お母様、お父様、そして祖父母様の衣装選びも大切です。「京都きもの友禅」なら、子どもの着物に合わせて親の訪問着やスーツもレンタル可能。クリーニング不要で、準備の手間なく、当日を笑顔で輝けるようにサポートします!
七五三は子どもが主役。親や家族の服装は華美になりすぎず、子どもの装いを引き立てるように整えるのが基本です。
神社への参拝・ご祈祷を伴うお祝いの場なので、家族も基本はフォーマルな服装が安心できますよ。
兄弟姉妹もきちんと感を意識すると写真映えし、統一感が出ます。
フォーマルといっても「シャツ+カーディガン+きれいめパンツ」など、ほどよく整えた装いで十分です。
ここでは母親・父親・祖父母や兄弟姉妹の服装について、さわりだけご紹介します。
母親の服装(和装・洋装)
七五三では母親は和装・洋装どちらでも構いませんが、子どもより控えめな装いが基本です。子どもが洋装で母親が和装という組み合わせは避けましょう。逆に、子どもが和装で母親が洋装の場合は問題ありません。和装なら訪問着や付け下げなど淡い色合いを選び、子どもの着物と調和させることが大切です。


▶ 七五三での母親の服装についてはこちらで詳しく解説しています
父親の服装(スーツ・和装)
父親は母親の装いに合わせつつ、子どもより目立たないことが基本です。子どもが明るい色の衣装なら、両親はネイビーや黒など落ち着いた色を選びましょう。
服装の選択肢はスーツ、略礼服、和装の3つ。スーツならダークカラーに白や淡色のシャツを合わせるのが無難です。略礼服はより格式を重視する場合に選ばれます。和装も近年人気で、無地や縞の着物+羽織で十分格式ある装いになります。ただし、父親が色紋付を着ると子どもより格上になるため避けましょう。


▶ 七五三での父親の服装についてはこちらで詳しく解説しています
祖父母や兄弟姉妹の服装
七五三は神社への参拝・ご祈祷を伴うお祝いの場。祖父母や兄弟姉妹も、主役を引き立てながらフォーマル感を意識すると、写真に残ったときに家族全体のまとまりが美しく映えます。
格としては「セミフォーマル」を意識し、落ち着きと清潔感を大切にすると安心です。
祖母の服装
祖母には、品のある装いが似合います。和装なら色無地や江戸小紋など落ち着いた色合いを、洋装ならネイビーやグレーのセレモニースーツがおすすめです。小物はパールのアクセサリーや上品なバッグを合わせ、履き慣れた靴で足元をすっきりまとめると、安心して一日を過ごせます。写真のようにシンプルな装いでも、小物次第で華やぎを添えられます。
祖父の服装
祖父はネイビーやチャコールグレーのダークスーツが基本。清潔感ある白シャツに控えめなネクタイを合わせ、磨かれた革靴で引き締めましょう。より格式を重んじたい場合には、紋付き羽織袴も選択肢になります。落ち着いた装いは、孫を見守る存在としての安心感を与えてくれます。

兄弟姉妹の服装
七五三では兄弟姉妹も一緒に写真に残ることが多いため、主役を引き立てながら家族全体の調和を意識すると美しくまとまります。服装は「清潔感」と「きちんと感」を意識すると安心です。
幼児は、動きやすさを第一に。フォーマル感のあるセットアップやワンピースに、白ソックスや落ち着いた色合いの靴を合わせると上品に仕上がります。華やかさを添えるために髪飾りや小さなコサージュをあしらうのもおすすめです。
小学生以上は、制服があれば着用するのが無難です。制服がない場合は、襟付きのシャツやジャケットを合わせると写真映えします。女の子はシンプルなワンピースにカーディガンを羽織ると季節感も出しやすく、男の子はネイビーやグレーのジャケットにベーシックなパンツでまとめると落ち着いた印象になります。
中学生以上は、大人に近いフォーマルを意識するとよいでしょう。男子ならスーツやブレザー、女子なら落ち着いた色合いのワンピースやセットアップがおすすめです。派手な色柄は避け、シンプルな装いにすることで、七五三の主役であるきょうだいをより引き立てられます。

▶ 七五三での祖父母・兄弟の服装についてはこちらで詳しく解説しています

11月15日が七五三の日になった理由

七五三といえば11月15日。この日が選ばれた理由にはいくつかの説があります。
まず、江戸時代に将軍・徳川綱吉が長男・徳松君の「髪置きの儀」を執り行ったのが11月15日だったと伝えられています。
この故事が武家社会に広まり、やがて庶民の間にも定着しました。
また、旧暦の11月は収穫を終えて神に感謝をささげる月でした。
その中でも15日は満月の日であり、特に縁起の良い日とされていました。
さらに、二十八宿という暦注で11月15日が「鬼宿日(きしゅくにち)」にあたり、鬼が出歩かない吉日であったことも理由のひとつとされています。
加えて「七・五・三」を足すと「十五」になることから、11月15日はお祝いの日としてふさわしいと考えられるようになりました。
こうした複数の由来が重なり、今日でも七五三は11月15日を中心に行われています。
ただし現代では、混雑を避けたり家族の予定に合わせたりして、10月から11月の吉日や週末に参拝するご家庭も増えています。
お宮参りとの関わり

七五三と並んで、子どもの成長を願う行事として大切にされてきたのが「お宮参り」です。
赤ちゃんが誕生してはじめて神社に参拝し、氏神様に新しい命を報告して無事な成長を祈る習わしです。
生後30日前後に行うのが一般的で、地域によっては男の子は31日目、女の子は32日目と日数を分けるところもあります。
昔は母親がまだ「忌明け」を迎えていないため、祖母や産婆が代わりに抱いて参拝することもありました。
今でも「七十五日参り」や「百日参り」として母子一緒にお参りする地域もあります。
本来は地元の氏神様へお参りするのが基本ですが、近年は写真撮影を兼ねて有名な神社に足を運ぶご家庭も多くなっています。
祈祷をお願いする際は、祝儀袋に「御初穂料」や「御玉串料」と記して納めるのが一般的です。
お宮参り、七五三、そして成人式へと、日本には子どもの成長を折々に祝う文化があります。
節目ごとに神様に感謝し、願いを込めることは、いつの時代も変わらない親心の表れといえるでしょう。
七五三の現代のかたち

七五三といえば本来は11月15日に行うものでしたが、今ではその日にこだわらず、10月から11月にかけて家族の予定や子どもの体調に合わせてお参りをするご家庭が増えています。
混雑を避けて平日に行ったり、写真は先に「前撮り」で残して、当日は参拝に集中したりと、スタイルはとても自由になっています。
服装も昔に比べて選択肢が広がりました。
和装でしっかりと晴れ姿を残すのも素敵ですし、洋装で動きやすさを重視するのも良い方法です。
どちらを選んでも、子どもの成長を喜び、記念の一日を大切に過ごすことに変わりはありません。
和装はやはり特別感があり、家族の思い出を華やかに彩ってくれる装いとして人気があります。
神社でのご祈祷は、地元の氏神様にお願いするのが昔ながらの形ですが、思い出作りを兼ねて有名な神社へ参拝するご家庭もあります。
どちらが正しいということはなく、「この子のために」という思いが込められていれば、どんな形でも七五三はかけがえのない行事になるのです。
七五三の形は時代とともに変わってきましたが、子どもの健やかな成長を願う親の心は、昔からずっと変わらずに受け継がれています。
[PR]
最高の記念を残すなら、神社での出張撮影という形も人気です。お子様の自然な笑顔を、プロが撮影。「ふぉとる」なら、無料の専門コンシェルジュがあなたにぴったりのカメラマンをご紹介。初めての方も安心です。
👉 まずは無料で相談してみる
よくあるQ&A

**Q1. 一人だけでもいいの?兄弟姉妹で一緒はNG?**
A. もちろん一人だけでも問題ありません。兄弟姉妹で一緒にお祝いするご家庭も多いです。神様にとって大切なのは、年齢や順番ではなく「子どもの無事な成長に感謝する心」です。
**Q2. 午後にお参りしても大丈夫?**
A. 大丈夫です。昔は午前中に参拝する習わしもありましたが、今ではご家庭の予定や子どもの体調に合わせて午後に行っても差し支えありません。大切なのは心を込めて参拝することです。
**Q3. 七五三は必ず11月15日に行わないといけませんか?**
A. 本来は11月15日が正式ですが、現代では10月〜11月の間で家族の都合のよい吉日や週末を選ぶことが一般的です。
**Q4. 七五三は数え年と満年齢、どちらで祝うべき?**
A. どちらでもかまいません。地域の習慣やご家庭の考え方によります。最近はわかりやすい満年齢で行うご家庭も増えています。
**Q5. 七五三の服装は洋装でも大丈夫?**
A. 大丈夫です。スーツやドレスで参拝する方もいますし、和装は特別感があり写真映えするため人気です。大切なのは「子どもの成長を祝う気持ち」です。
**Q6. 七五三のお参りはどこの神社に行けばいいの?**
A. 本来は地元の氏神様ですが、最近は有名な神社や写真撮影に合わせて参拝先を選ぶ方も多いです。どちらも間違いではありません。
**Q7. 初穂料はいくらぐらいが相場?**
A. 神社によって異なりますが、5,000円〜10,000円程度が一般的です。のし袋には「御初穂料」や「御玉串料」と書いて納めます。
まとめ
七五三は、子どもの成長を感謝し、これからの幸せを願うために受け継がれてきた大切な行事です。
平安時代の通過儀礼に始まり、江戸時代を経て、今では全国のご家庭で親しまれるようになりました。
時代が変わり、参拝の日にちや服装のスタイルはご家庭ごとに自由に選べるようになりました。
それでも変わらないのは「無事にここまで育ってくれてありがとう」「これからも元気でいてほしい」という親の気持ちです。
七五三は、その気持ちをあらためて形にできる、かけがえのない節目の日なのです。
お子さんの晴れ姿を見守りながら、ご家族にとって心に残るあたたかな一日になりますように。
関連記事はこちら
✿コラム:Fumi’s Kimono Diary ✿
先日、七五三の撮影に立ち会う機会がありました。
三歳の女の子は小さな「三つ身」に被布を羽織って、まだ帯を結ばない姿がなんとも可愛らしく、歩くたびに裾がふわりと揺れていました。
五歳の男の子は羽織袴を着て、最初は緊張で表情がかたかったのに、カメラの前で扇子を広げると急に得意げな顔に。
七歳の女の子は四つ身の着物に帯を結び、鏡の前で自分の姿を見つめている姿が、もう小さな淑女のようでした。
「七歳までは神のうち」といわれた昔と比べると、今は元気に成長していることが当たり前のように思えます。
でも、あらためて着物姿のお子さんを見ていると、「ここまで大きくなってくれてありがとう」と胸がいっぱいになるのは、今も昔も変わらないのだなと感じます。
七五三は、親にとっても子どもにとっても、家族みんなの記憶に残る日。着物がその節目を彩る姿を見守れることは、ほんとうに幸せなことですね。